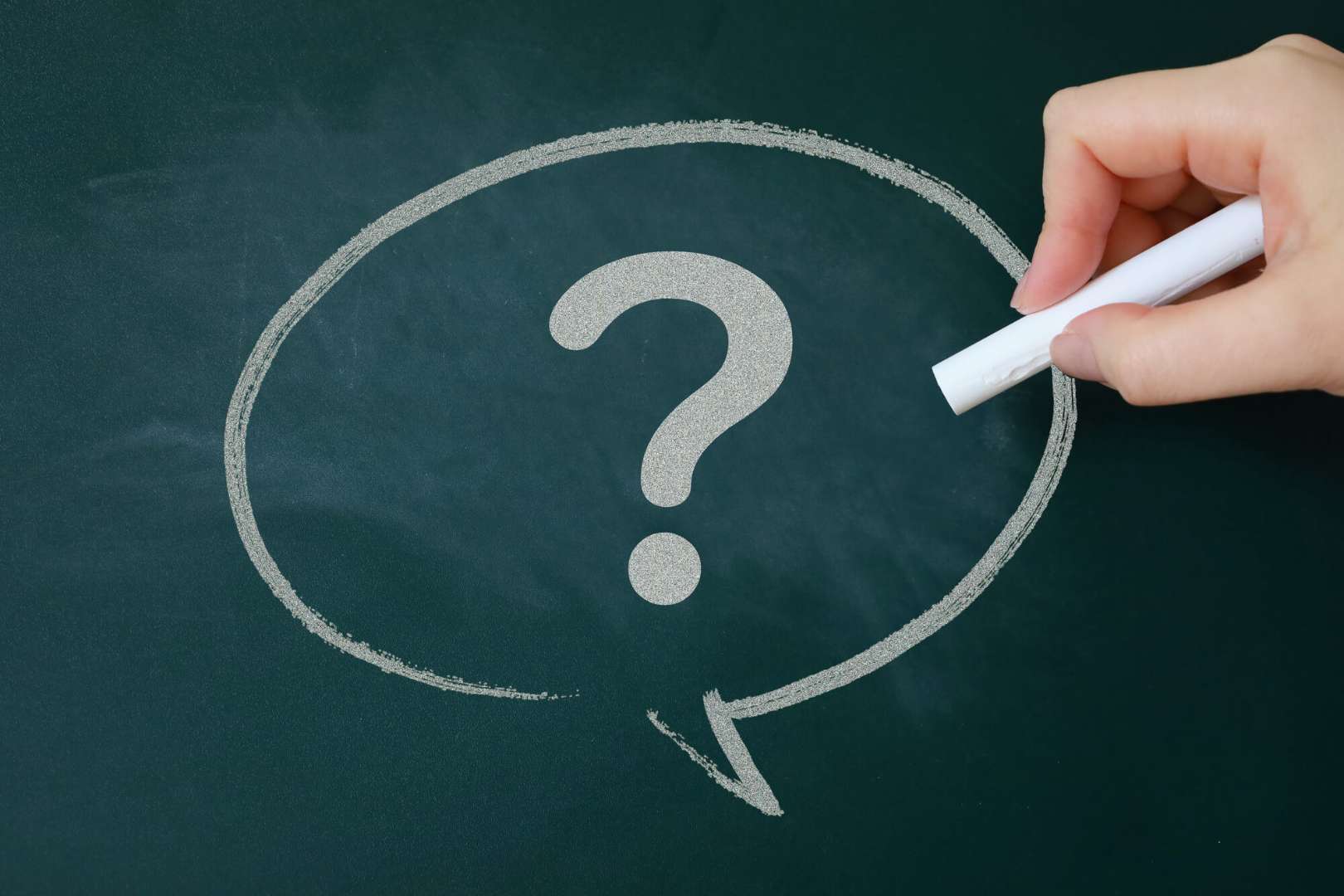トラックドライバーの仕事は、一見すると「運転しているだけ」と思われがちですが、実際には長時間にわたって座り続けることが多く、体を動かす機会が限られています。運転が主な業務である以上、腰や肩まわりに負担がかかりやすく、同じ姿勢が続くことで血行も悪くなりがちです。また、勤務時間が不規則だったり、休憩中もトラックの中で過ごすことが多いため、「気づけば1日ほとんど歩いていない」という日も珍しくありません。
その結果、体重が増えたり、慢性的な腰痛に悩まされたりするドライバーも少なくなく、「このままでは体がもたないのでは」と不安を感じる方もいるでしょう。特に30代以降になると、体力の低下を実感し始めるタイミングと重なり、健康面の課題が表面化しやすくなります。
とはいえ、仕事の性質上、急に運動時間を確保するのは簡単ではありません。だからこそ、無理なく取り入れられる方法や、実際に現場で実践されている工夫を知っておくことが大切です。この記事では、運動不足に陥りがちな理由や、それでも体を守るための具体的な考え方について、現場目線で掘り下げていきます。
なぜ運転手は運動不足になりやすいのか、仕組みで解説
トラックドライバーが運動不足になりやすい背景には、業務の構造そのものが大きく関係しています。まず、1日の大半を運転席で過ごすことが当たり前という勤務形態があります。長距離ドライバーであれば、数時間単位でノンストップの運行が続くこともあり、1日1万歩どころか、数百歩程度しか歩かない日もあります。
さらに、積み込みや荷下ろしの際に体を動かす場面はあるものの、それも業務時間全体の中ではごくわずかです。運行ルートや荷物の種類によっては、体を動かす機会がほとんどないまま1日を終えることも珍しくありません。休憩時間中も、サービスエリアのベンチやトラックの運転席で仮眠を取ることが多く、「意識的に動こうとしない限り、体はほぼ止まったまま」です。
また、時間的な余裕がないという現実もあります。納品の時間指定や渋滞などの予期せぬ遅れへの対応などで、計画どおりに動けない日が多く、運動に時間を割こうという気持ちがあっても、現実にはなかなか難しい。加えて、運転後の疲労感も大きいため、帰宅後に運動する余力が残っていないことも多いです。
このように、トラックドライバーという職業は、日常的に体を動かす仕組みがほとんど組み込まれていません。業務内容や働き方がそうなっている以上、本人の意識だけでカバーするのには限界があります。だからこそ、「運動不足になってしまうのは自分のせい」ではなく、仕事の構造に目を向けることが第一歩になります。
腰痛・肥満・生活習慣病…運動不足を放っておくと?
運動不足の状態が続くと、最初にあらわれるのが腰や肩の痛みです。特に長時間同じ姿勢で座り続けることが多いトラックドライバーにとって、腰まわりの筋力低下は深刻な問題です。最初は違和感程度だったものが、ある日突然ギックリ腰になるケースもあり、現場では「あるある話」として語られることもあるほどです。
また、体を動かす機会が少ないと、代謝が落ちて体重が増えやすくなります。とくに夜間の運行や不規則な食事が重なると、食べた分がそのまま脂肪として蓄積されやすく、気づけば健康診断で「メタボ予備軍」と言われる人も増えていきます。これは見た目だけの問題ではありません。血圧や血糖値、コレステロール値の上昇といった生活習慣病のリスクにもつながります。
さらに深刻なのは、こうした体調不良が「仕事の継続」にも影を落とすことです。健康を崩して休職を余儀なくされたり、再就職が難しくなったりする事例も現実にあります。若いうちは気力で乗り切れても、年齢とともに回復力は確実に落ちていきます。だからこそ、早い段階から自分の体と向き合う姿勢が求められるのです。
「多少の痛みは仕方ない」と我慢し続けてしまう人もいますが、放置すればするほど回復に時間がかかり、治療費もかさみます。大切なのは、症状が出てから対処するのではなく、なるべく出さない工夫を積み重ねること。運動不足による影響はじわじわと表面化するからこそ、今日からできる小さな意識が将来の自分を守る第一歩になります。
「時間がない人向け」無理せず続く対策とは?
運動不足の解消といっても、「ジムに通う」「ランニングを始める」といった時間や場所を必要とする方法は、トラックドライバーにとって現実的ではありません。むしろ、運行の合間や休憩中など、わずかなスキマ時間をどう活用するかが鍵になります。無理なく続けられる小さな習慣が、結果的に大きな差を生みます。
たとえば、荷下ろし後に5分だけストレッチを取り入れる。腰や太ももまわりを中心に軽く動かすだけでも、血流の促進や疲労の軽減につながります。また、信号待ちやトラックの停車中に座ったままできる簡単な体操(つま先の上げ下げや肩甲骨まわりの動作)も、日常的なこりやむくみの予防に効果的です。
歩数を増やしたい場合は、休憩所やパーキングエリアでトイレまで遠回りする、あえて階段を使うなどの小さな工夫で対応できます。何かを「始める」よりも、すでにある行動に少しだけ運動要素を足す考え方が、継続のコツです。
最近では、運動習慣の記録を手軽につけられるアプリも多く、スマートフォンで1日の歩数やストレッチ回数を可視化することで、やる気を維持しやすくなります。仲間と一緒に「今日は何歩歩けたか」を共有するだけでも、ちょっとした励みになることがあります。
会社によっては、健康管理に力を入れているところもあり、定期的な体操指導や健康診断の充実、運行スケジュールの調整などを通じて、社員の体づくりを支援しているケースもあります。働く環境そのものが変われば、個人の努力に頼りきらずとも自然と体を動かせるようになります。
全部やらなくていい。1つでも意識すれば十分
運動不足を解消しようと考えたとき、「毎日やらなきゃ」「全部ちゃんとやらなきゃ」と気負ってしまう人も少なくありません。しかし、トラックドライバーの仕事は時間も体力も限られており、完璧を目指すと逆に続きません。大切なのは、「できることを1つだけでも続ける」こと。たとえ毎日じゃなくても、週に数回でも、意識して体を動かそうとする気持ちがあれば、それはもう立派な取り組みです。
たとえば、運転前に背伸びをする。休憩中に5分だけ歩く。これだけでも体は変わってきます。人と比べる必要はありませんし、今日できなかったからといって自分を責める必要もありません。健康を保つための第一歩は、続けるための「自分なりのペース」を見つけることです。
また、体の不調に気づいたときこそチャンスです。「これはマズいかも」と思えたなら、それは変わるきっかけになります。痛みや違和感をごまかすのではなく、少しでも楽になるように体を気づかう行動ができれば、自然と意識も前向きに変わっていきます。
そして、職場の理解やサポートがあるかどうかも大きな要素です。無理な運行スケジュールが組まれていないか、休憩時間がしっかり確保されているか、健康面に配慮してくれる風土があるか。自分ひとりで頑張り続けるのではなく、環境そのものが改善されれば、自然と体を大事にしながら働けるようになります。
そんな働きやすい環境を重視している会社を探したい方は、こちらも参考にしてみてください。
▶︎ https://www.tsubasa-exp.jp/recruit
大切なのは、「続ける体」をどう作るか
トラックドライバーという仕事は、体が資本です。長く続けるには、まず自分の体をどう守るかを考えることが欠かせません。ただ、日々の忙しさのなかで「健康を気にする余裕なんてない」と感じるのも無理はありません。だからこそ、完璧を目指すのではなく、小さな気づきや行動から始めていくことが何より大切です。
1分でもいい。歩幅を少し広げてみる、背筋を伸ばしてみる。それだけでも体は応えてくれます。無理をせず、でも放っておかない。そんな向き合い方が、仕事も生活も、少しずつ楽にしてくれます。
今の働き方や体調について、少しでも引っかかることがあれば、遠慮せず誰かに相談してみることをおすすめします。話すことで見えてくる選択肢もきっとあります。
▶︎ お問い合わせはこちらから